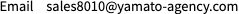BIM/CIM関連用語
-
BIM(Building Information Modeling)
建物の3次元デジタルモデルに、部材の仕様や性能、コストなどの属性情報を付加した建築情報モデル。設計から施工、維持管理まで一貫して活用でき、関係者間の情報共有や合意形成を効率化します。
-
CIM(Construction Information Modeling)
土木分野におけるBIMの概念。道路、橋梁、トンネルなどの土木構造物の3次元モデルに属性情報を付加し、計画・設計・施工・維持管理の各段階で活用する手法です。2023年度から国土交通省の直轄工事で原則適用されています。
-
LOD(Level of Development/Detail)
BIM/CIMモデルの詳細度・成熟度を示す指標。LOD100(概念設計)からLOD500(竣工モデル)まで段階的に定義され、プロジェクトの進捗に応じて必要な詳細度を明確化。例えばLOD300では正確な寸法・位置情報を含み、LOD400では製作・組立情報まで網羅。発注者と受注者間でのモデル要求水準の共通認識形成に不可欠。
-
CDE(Common Data Environment)
BIM/CIMプロジェクトにおける共通データ環境。プロジェクト関係者が設計データ、図面、仕様書などを一元管理・共有するためのデジタルプラットフォーム。アクセス権限管理、バージョン管理、承認ワークフロー機能を備え、最新情報への確実なアクセスと作業の重複防止を実現。ISO19650で国際標準化されている。
-
IFC(Industry Foundation Classes)
建設業界の国際的なデータ交換標準フォーマット。異なるBIMソフトウェア間でのデータ互換性を確保し、ベンダーロックインを防ぐ。建物の形状情報だけでなく、材料特性、空間関係、設備システムなどの意味情報も含む。buildingSMARTが策定・管理し、ISO16739として国際標準化されている。
i-Construction・国交省関連用語
-
i-Construction
国土交通省が2016年から推進する建設現場の生産性革命プロジェクト。ICT技術の全面的な活用により、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全プロセスで生産性を向上。3つの柱は「ICT土工」「規格の標準化」「施工時期の平準化」。2025年までに建設現場の生産性を2割向上させる目標を掲げ、ドローン測量、ICT建機による施工、3次元データ納品などが標準化されつつある。
-
NETIS(New Technology Information System)
国土交通省が運営する新技術情報提供システム。民間企業が開発した新技術・新工法の情報を共有し、公共工事での活用を促進。登録技術は活用効果評価を経て、有用な技術として認定される。登録により工事成績評定での加点対象となるため、建設会社の技術開発インセンティブとしても機能。約3,000件の技術が登録され、検索・比較が可能。
-
電子小黒板
でんしこくろばん
工事写真撮影時にデジタル情報を付加する電子的な黒板機能。従来の木製黒板に代わり、タブレットやスマートフォンのアプリで工事情報(工事名、撮影日時、測点等)を写真に直接記録。改ざん防止機能により信頼性を確保し、国土交通省の工事でも使用が認められている。写真整理の効率化と黒板持ち運びの労力削減を実現。
-
情報共有システム(ASP)
工事関係者間で図面・書類等を共有するクラウド型システム。国土交通省では「工事帳票管理システム」として標準化を推進。受発注者間での書類提出・承認プロセスをデジタル化し、移動時間削減と意思決定の迅速化を実現。電子納品との連携により、工事完成時の成果品作成も効率化。月額利用料での導入が可能で中小企業でも活用しやすい。
-
電子納品
工事完成図書を電子データで納品する仕組み。国土交通省が定める「電子納品要領」に基づき、CAD図面はSXF形式、写真はJPEG形式など、長期保存に適した標準フォーマットで作成。CD-RやDVD-Rで納品し、保管スペース削減と検索性向上を実現。CALS/ECの一環として、建設生産システム全体の効率化に寄与している。
現場管理DX用語
-
デジタルツイン
現実の建設現場や構造物をデジタル空間に再現した仮想モデル。IoTセンサーからのリアルタイムデータを反映し、現実と同期した状態を維持。施工シミュレーション、進捗管理、安全性検証などに活用。例えば重機の稼働状況、作業員の動線、資材の配置などを仮想空間で可視化し、最適な施工計画の立案や危険予知に活用できる。維持管理段階では劣化予測や補修計画にも応用される
-
IoT(Internet of Things)
建設現場の各種機器・センサーをインターネットに接続し、データ収集・分析を行う技術。コンクリート養生温度センサー、建機の稼働監視、作業員のバイタルセンサーなど多様な活用例がある。収集データはクラウドに集約され、異常検知や予防保全に活用。現場の見える化により、生産性向上と安全管理の高度化を同時に実現する。
-
GNSS(Global Navigation Satellite System)
GPS、GLONASS、Galileo、準天頂衛星「みちびき」などの衛星測位システムの総称。建設現場では、ICT建機の自動制御、ドローン測量、出来形管理などに活用。RTK-GNSS(リアルタイムキネマティック)により誤差数センチメートルの高精度測位が可能。従来の光波測量と比べ、基準点設置の手間が削減され、リアルタイムでの施工管理が実現する。
-
点群データ
レーザースキャナーやドローン写真測量により取得される3次元座標を持つ点の集合データ。地形や構造物の形状を高密度(1平方メートルあたり数百~数千点)で記録。土工事の出来高管理、既存構造物の維持管理、BIM/CIMモデル作成の基礎データとして活用。点群処理ソフトウェアにより、断面図作成、土量計算、変位解析などが効率的に実施できる。
-
ICT建機
情報化施工に対応した建設機械。3次元設計データと衛星測位システムを組み合わせ、オペレーターの熟練度に依存しない高精度施工を実現。マシンコントロール(自動制御)とマシンガイダンス(操作支援)の2種類があり、ブルドーザー、油圧ショベル、グレーダーなどで実用化。施工精度向上、工期短縮、省力化を同時に達成し、経験の浅いオペレーターでも熟練者並みの施工が可能。
-
ビルディングOS
建物の各種システムを統合制御するソフトウェア基盤。空調、照明、セキュリティ、エレベーターなどを一元管理し、最適運用を実現。AIによる需要予測と自動制御により、エネルギー消費を20-30%削減。建設段階からBIMデータと連携し、竣工後の運用データを設計にフィードバック。スマートビルディングの中核技術として、建物のライフサイクル全体での価値最大化に貢献。
-
リーン・コンストラクション
製造業のリーン生産方式を建設業に適用した管理手法。無駄の排除、継続的改善、ジャストインタイムを原則とする。ラストプランナーシステムにより、週間作業計画の達成率を向上。プルプランニングで後工程から前工程への要求を明確化し、手待ちを削減。タクトタイム管理により、工程の平準化を実現。日本のトヨタ生産方式が起源で、欧米建設業界で発展した手法。
安全管理・労務管理DX用語
-
ウェアラブルデバイス
作業員が身に着けるICT機器。スマートウォッチ、スマートヘルメット、バイタルセンサー付き作業服などが代表例。心拍数、体温、位置情報をリアルタイム監視し、熱中症予防や危険エリアへの接近警告を実現。転倒検知機能により、事故発生時の迅速な救助も可能。収集データは作業員の健康管理や労務管理にも活用され、働き方改革にも貢献している。
-
顔認証システム
建設現場の入退場管理や作業員の本人確認に使用される生体認証技術。従来のICカード方式と比べ、なりすまし防止や紛失リスクがない。複数現場を渡り歩く作業員の勤怠管理を一元化し、建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携により技能者の就業実績を正確に記録。マスク着用時でも認証可能な最新システムも登場している。
-
AI画像解析
建設現場の監視カメラ映像をAIが解析し、危険行動や異常を自動検知する技術。ヘルメット未着用、立入禁止区域への侵入、不安全行動などをリアルタイムで検出し、警告を発する。蓄積データから危険予知や安全教育への活用も可能。人による監視の限界を補完し、24時間365日の安全管理を実現。プライバシーに配慮した骨格検知技術の採用事例も増えている。
-
デジタルサイネージ
建設現場の朝礼広場や詰所に設置される大型ディスプレイ。安全指示、作業工程、気象情報などをリアルタイム表示。緊急時には避難経路や警報を即座に表示可能。多言語対応により外国人労働者への情報伝達も確実に。ペーパーレス化と情報の一元化により、伝達ミスを防止し、現場のコミュニケーション向上に寄与する。
-
CCUS(建設キャリアアップシステム)
技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴などを業界統一で登録・蓄積する仕組み。ICカードを現場のカードリーダーにかざすことで、就業実績が自動記録される。技能者の適正な評価と処遇改善、社会保険加入の徹底を目的とし、2019年から本格運用開始。蓄積データは技能者のキャリア証明として活用され、建設業の担い手確保にも貢献。
図面・書類管理DX用語
-
OCR(Optical Character Recognition)
紙図面や手書き書類をスキャンしてデジタルテキスト化する光学文字認識技術。建設業では古い図面のデジタル化、野帳の電子化、検査記録の整理などに活用。AI-OCRの登場により、手書き文字や建設特有の専門用語の認識精度が向上。認識したテキストは検索可能となり、膨大な過去資料から必要な情報を瞬時に抽出できる。図面内の寸法値や注記の自動読み取りも可能に。
-
クラウドストレージ
インターネット経由でデータを保存・共有するサービス。建設現場では図面、写真、書類などを現場事務所のサーバーではなくクラウド上で管理。容量制限を気にせず、現場・本社・協力会社間でリアルタイムな情報共有が可能。自動バックアップによりデータ消失リスクを軽減。アクセス権限を細かく設定でき、機密情報の管理も安全に行える。
-
ワークフロー
書類の申請・承認プロセスを電子化したシステム。建設業では施工計画書、材料承認願、安全書類などの承認フローをデジタル化。承認者不在による遅延を防ぎ、承認履歴も自動記録。スマートフォンからも承認可能で、現場にいながら迅速な意思決定を実現。ペーパーレス化によるコスト削減と、内部統制強化の両立が可能。
-
電子署名
デジタル文書に付与する電子的な署名。印鑑に代わる本人確認手段として、建設業でも契約書、見積書、検査記録などで活用が進む。PKI(公開鍵基盤)技術により改ざん防止と本人性を保証。タイムスタンプと組み合わせることで、文書の存在時刻も証明可能。リモートワークでも契約業務が完結し、印紙税削減のメリットもある。
-
BPM(Business Process Management)
業務プロセスを可視化・最適化する管理手法とそれを支援するシステム。建設業では見積から施工、竣工までの一連のプロセスを標準化・自動化。各工程の所要時間や滞留箇所を分析し、ボトルネックを特定・改善。ISO9001などの品質管理システムとも連携し、継続的な業務改善を実現。属人化していた業務の標準化により、技術継承にも貢献。
通信・ネットワーク関連用語
-
5G(第5世代移動通信システム)
高速・大容量・低遅延・多接続を特徴とする次世代通信規格。建設現場では4K映像のリアルタイム伝送、遠隔操作重機の精密制御、多数のIoTセンサー同時接続などに活用。ローカル5Gにより現場専用の通信環境構築も可能。遅延1ミリ秒以下により、危険作業の遠隔化や、本社からの遠隔臨場が実用レベルに。通信インフラが整備されていない山間部でも、可搬型基地局により高速通信を実現。
-
エッジコンピューティング
データ処理をクラウドではなく現場(エッジ)側で行う分散処理技術。建設現場では監視カメラの映像解析、センサーデータの一次処理などに活用。通信遅延の影響を受けず、リアルタイムな判断が必要な安全管理に有効。通信コスト削減、プライバシー保護の観点からも注目される。現場に設置したエッジサーバーで処理し、必要なデータのみクラウドに送信する構成が一般的。
-
VPN(Virtual Private Network)
インターネット上に仮想的な専用線を構築する技術。建設現場と本社間で機密情報を安全に通信。現場事務所から社内システムへの安全なアクセスを実現し、テレワーク環境でも活用。IPsec-VPNやSSL-VPNなど複数の方式があり、用途に応じて選択。BIM/CIMデータなど大容量ファイルの送受信でも、セキュリティを確保しながら効率的な共有が可能。
-
API(Application Programming Interface)
異なるソフトウェア間でデータをやり取りするための仕組み。建設業では積算ソフトと会計システム、BIMソフトと施工管理システムなどの連携に活用。手作業でのデータ転記を削減し、ヒューマンエラーを防止。オープンAPIにより、ベンダーの異なるシステム間でも柔軟な連携が可能。建設DXの基盤技術として、データのサイロ化を防ぐ重要な役割を担う。
-
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)
最新の無線LAN規格。従来のWi-Fi 5と比べ約1.4倍の高速化、多台数同時接続時の安定性向上を実現。建設現場では多数のタブレット、スマートフォン、IoT機器が同時接続される環境で威力を発揮。省電力機能によりバッテリー駆動機器の運用時間も延長。メッシュWi-Fi技術と組み合わせることで、広大な現場全体をカバーする通信環境を構築可能。
施工管理システム関連用語
-
ERP(Enterprise Resource Planning)
企業資源計画システム。建設業向けERPでは、受注から施工、原価管理、労務管理までを統合管理。プロジェクトごとの収支をリアルタイムに把握し、赤字工事の早期発見が可能。材料・労務・外注費などの原価要素を一元管理し、過去の類似工事データから精度の高い見積作成も支援。経営判断に必要な情報を可視化し、データドリブンな経営を実現する基幹システム。
-
WBS(Work Breakdown Structure)
プロジェクトを階層的に分解した作業分解構成図。建設工事では工種別、工程別に作業を細分化し、原価管理や進捗管理の単位として活用。各作業に責任者、期限、予算を割り当て、プロジェクト全体の見える化を実現。デジタル化により、WBSと連動した自動進捗集計や、遅延作業の影響範囲分析が可能に。国際的なプロジェクト管理手法としても標準化されている。
-
ガントチャート
工程管理を時系列で可視化する横棒グラフ。建設現場では全体工程から日々の作業計画まで幅広く活用。クリティカルパス(最重要工程)の明確化により、工期遅延リスクを事前に把握。クラウド型工程管理システムでは、関係者全員がリアルタイムに進捗を共有可能。天候や資材納期の変更にも柔軟に対応し、最適な工程再計画を支援。
-
EVMS(Earned Value Management System)
出来高による進捗管理手法。計画値(PV)、実績値(EV)、実際原価(AC)の3つの指標から、コストと工程を統合的に管理。建設プロジェクトの健全性を定量的に評価し、完成時のコスト・工期を高精度で予測。進捗遅れや予算超過の兆候を早期発見し、是正措置の意思決定を支援。国土交通省の大規模工事でも導入が進んでいる。
-
BIツール(Business Intelligence)
蓄積データを分析・可視化し、経営判断を支援するシステム。建設業では工事実績データ、原価データ、安全データなどを多角的に分析。ダッシュボード機能により、KPI(重要業績評価指標)をリアルタイム監視。過去の失敗事例から学習し、リスク予測も可能。現場担当者でも簡単にレポート作成でき、データに基づく改善活動を促進。
新技術・先端技術用語
-
ドローン(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)
無人航空機。建設現場では測量、進捗管理、検査、安全パトロールなど多岐にわたり活用。写真測量により数センチメートル精度の3次元地形データを短時間で取得可能。赤外線カメラ搭載により、コンクリート構造物の劣化診断も実施。自動飛行プログラムにより、定期的な進捗記録を省力化。国土交通省の「UAVを用いた公共測量マニュアル」により、公共工事での活用が標準化されている。
-
AI(Artificial Intelligence)
人工知能技術。建設業では画像認識による品質検査、需要予測による資材管理、自然言語処理による書類作成支援など幅広く活用。機械学習により、過去の工事データから最適な施工計画を提案。異常検知AIは、構造物の微細な変化を察知し予防保全に貢献。熟練技術者の暗黙知をAIに学習させることで、技術継承の課題解決にも期待される。
-
ロボット施工
建設作業の自動化・省人化を実現するロボット技術。鉄筋結束ロボット、溶接ロボット、清掃ロボットなどが実用化。繰り返し作業や危険作業をロボットが代替し、作業員は管理・監督業務に専念。協働ロボット(コボット)は人と同じ空間で安全に作業可能。少子高齢化による労働力不足対策として期待され、生産性向上と労働環境改善を同時に実現。
-
デジタルファブリケーション
3Dプリンター、レーザーカッター、CNCなどデジタルデータから直接製造する技術。建設業では複雑な形状の型枠製作、建築模型作成、特殊部材の製造などに活用。3Dコンクリートプリンターは、型枠不要で自由曲面の構造物を造形可能。設計データから製造までをシームレスに連携し、手戻りゼロのものづくりを実現。マスカスタマイゼーションにより、個別ニーズへの対応も容易に。
-
ブロックチェーン
改ざん困難な分散型台帳技術。建設業では契約管理、サプライチェーン管理、品質証明などに応用。工事の各工程で発生する検査記録や承認履歴を改ざん不可能な形で記録。建材のトレーサビリティ確保により、偽装防止や品質保証を強化。スマートコントラクトにより、工事の進捗に応じた自動支払いも実現可能。信頼性の高い情報共有基盤として注目される。
-
ジェネレーティブ・デザイン
AIが設計条件(荷重、材料、コスト等)から無数の設計案を自動生成する技術。建設業では構造部材の最適形状、鉄骨フレームの軽量化設計などに活用。人間では思いつかない革新的な形状を提案し、材料使用量を最大40%削減した事例も。Autodesk Fusion 360などのソフトウェアで実装され、サステナブルな建築設計を支援。自然界の形態を模倣したバイオミメティクス設計も可能に。
-
コンピュテーショナル・デザイン
アルゴリズムとプログラミングを用いた設計手法。Grasshopper、Dynamoなどのビジュアルプログラミング環境で、パラメトリックな建築設計を実現。複雑な曲面を持つファサードの最適化、日照シミュレーションに基づく開口部配置など、性能に基づく設計が可能。設計変更時も自動的に関連要素が更新され、手戻りを大幅削減。建築家とエンジニアの協働を促進する。
-
リアリティ・キャプチャ
現実空間を高精度でデジタル化する技術群。フォトグラメトリ、レーザースキャン、NeRF(Neural Radiance Fields)などを統合活用。建設現場では既存建物の改修工事前調査、施工進捗の記録、竣工時の現況保存に活用。数百枚の写真から高精度3Dモデルを自動生成し、点群データとBIMモデルの照合により施工精度を検証。文化財建築のデジタルアーカイブにも応用される。
リモート・遠隔技術用語
-
遠隔臨場
発注者の監督員が現場に行かずに、映像・音声により段階確認や材料確認を行う仕組み。ウェアラブルカメラやタブレットを使用し、リアルタイムで現場状況を共有。移動時間削減により、監督員は複数現場を効率的に管理可能。国土交通省が推進し、コロナ禍を機に急速に普及。映像記録により、後日の確認も可能となり、施工管理の透明性が向上。
-
デジタルサイン
建設現場の案内板、安全標識、工程表示などをデジタル化した電子掲示板。従来の印刷物と異なり、情報をリアルタイムで更新可能。多言語切替機能により、外国人作業員への情報伝達も確実に。緊急時には警報表示に切り替わり、避難誘導にも活用。省エネLEDバックライトと防塵防水設計により、屋外での長期使用にも対応。ペーパーレス化によるコスト削減効果も大きい。
-
テレマティクス
建設機械の稼働状況を遠隔監視する車両管理システム。GPSによる位置情報、エンジン稼働時間、燃料消費量、故障診断情報などをリアルタイム収集。盗難防止、稼働率向上、予防保全に活用。複数メーカーの建機を一元管理できるプラットフォームも登場。稼働データの分析により、最適な機械配置や更新時期の判断も可能。レンタル会社との情報共有により、機械手配の効率化も実現。
-
VR(Virtual Reality)
仮想現実技術。建設業では安全教育、施工シミュレーション、完成イメージの共有などに活用。高所作業や重機操作の危険性を、安全な環境で体験学習。BIMデータと連携し、建物内部を施工前にウォークスルー可能。施主への提案時には、完成後の空間を没入体験してもらうことで、合意形成を促進。メタバース化により、遠隔地からの共同設計レビューも実現している。
-
AR(Augmented Reality)
拡張現実技術。現実の建設現場に、設計図面や配管ルートなどのデジタル情報を重ね合わせて表示。タブレットやスマートグラスを通して、地中埋設物の位置や完成後の姿を可視化。施工ミスの防止、手戻り削減に効果的。保守点検では、機器の整備履歴や操作手順をAR表示し、作業効率を向上。MR(複合現実)への発展により、より高度な現実とデジタルの融合が進んでいる。
データ活用・標準化用語
-
オープンデータ
国際標準化機構が定める建設分野のデータ規格。ISO19650(BIM)、ISO15686(ライフサイクルコスティング)など、グローバルな相互運用性を確保。日本の建設業界もJIS化を通じて国際標準に準拠。データの長期保存性と互換性を保証し、ベンダーロックインを防止。国際プロジェクトでの協業や、海外展開時の技術的障壁を低減する効果もある。
-
メタデータ
データに関する付加情報。建設業では図面の作成者、作成日時、改訂履歴、座標系、縮尺などの管理情報。写真データには撮影位置、撮影日時、工事名などを自動付与。適切なメタデータ管理により、膨大なデータから必要な情報を効率的に検索可能。データの信頼性確保と、長期的なアーカイブ管理の基盤となる。AI学習用データセットの品質管理にも不可欠。
-
ETL(Extract, Transform, Load)
異なるシステムからデータを抽出、変換、格納する一連のプロセス。建設業では、現場の日報データ、原価システム、勤怠システムなど複数のデータソースを統合。データクレンジングにより、表記ゆれや欠損値を修正し、分析可能な形式に整形。定期的な自動実行により、経営ダッシュボードへのリアルタイムなデータ供給を実現。ビッグデータ活用の前処理として重要な役割を担う。
-
デジタルトランスフォーメーション(DX)
デジタル技術により業務プロセス、企業文化、顧客体験を根本的に変革すること。建設業では単なるICT導入にとどまらず、データドリブンな意思決定、新たなビジネスモデル創出を目指す。BIM/CIMを核とした情報の一元化、AI・IoTによる自動化、プラットフォーム型ビジネスへの転換などが進行。2024年問題への対応も含め、持続可能な建設業への変革が求められている。
プラットフォーム・ビジネスモデル用語
-
コンストラクション・テック(ConTech)
建設業界向けのテクノロジー企業・サービスの総称。施工管理アプリ、ドローン測量、AI画像解析、マッチングプラットフォームなど多岐にわたる。世界的にはProcore、PlanGrid、Katerra等が代表例。日本でもANDPAD、SPIDERPLUS、Photoructionなどが急成長。建設業の課題をテクノロジーで解決し、業界のデジタル変革を加速。ベンチャー投資も活発化し、新たなエコシステムを形成している。
-
プロパティ・テック(PropTech)
不動産業界のテクノロジー革新。建設業との境界領域では、BIMデータを活用した不動産管理、IoTセンサーによるビル運営最適化、VRによる竣工前内覧などが実現。建設段階から運用段階までのデータ連携により、建物のライフサイクル価値を最大化。スマートビルディング、デジタルツインなど、建設と不動産の融合が進む。ESG投資の観点からも注目度が高まっている。
-
SaaS(Software as a Service)
クラウド経由で提供されるソフトウェアサービス。建設業では工程管理、原価管理、安全管理などの基幹業務がSaaS化。初期投資不要、常に最新版利用可能、どこからでもアクセス可能などのメリット。Box、Dropboxなどの汎用サービスから、建設業特化型のFieldwire、PlanRadarまで選択肢は多様。月額課金により中小企業でも導入しやすく、DXの入口として機能。
-
オフサイト・コンストラクション
工場や専用施設で建築部材を製造し、現場で組み立てる工法。プレキャスト・コンクリート、鉄骨ユニット、CLT(直交集成板)などが代表例。天候に左右されない安定生産、品質管理の向上、現場作業員の削減を実現。BIMデータから直接製造機械を制御し、ミリ単位の精度を確保。モジュール化により、解体・再利用も容易。建設業の製造業化として注目される。
-
クロス・リアリティ(XR)
VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)を包括する概念。建設業では設計レビュー、施工シミュレーション、保守点検支援など全工程で活用。Microsoft HoloLens、Magic Leap等のデバイスにより、現場でのハンズフリー作業を実現。複数人が同じ仮想空間を共有し、遠隔地からの技術指導も可能。メタバース建築など、新たなビジネスモデルも生まれている。
電子黒板・液晶ディスプレイ関連用語
-
インタラクティブホワイトボード(IWB)
タッチ操作可能な大型電子黒板。建設現場では図面への直接書き込み、拡大縮小、複数画面の同時表示などが可能。赤外線方式、静電容量方式、電磁誘導方式などタッチ検出技術は多様。20点以上の同時タッチに対応し、複数人での協働作業を実現。手袋着用時でも操作可能な機種は、建設現場での実用性が高い。データ保存機能により、打合せ内容の記録・共有も容易。
-
4K/8K解像度
超高精細映像規格。4K(3840×2160)は従来のフルHDの4倍、8K(7680×4320)は16倍の解像度。建設図面の細部表示、BIMモデルの精密表現に威力を発揮。CAD図面の細かい寸法値や注記も、拡大せずに視認可能。大画面でも画素の粗さが目立たず、長時間の作業でも目の疲労を軽減。DisplayPort1.4やHDMI2.1など、高速伝送規格への対応も重要。
-
輝度(cd/m²)
ディスプレイの明るさを示す単位。建設現場向けは350〜500cd/m²が標準的で、屋外使用モデルは1000cd/m²以上。高輝度により、明るい現場事務所や直射日光下でも視認性を確保。自動輝度調整機能により、周囲の明るさに応じて最適な輝度に調整。省エネと視認性のバランスを考慮し、使用環境に応じた輝度設定が重要。
-
マルチタッチ
複数の指やタッチペンでの同時操作を認識する技術。ピンチイン・アウトでの拡大縮小、2本指でのスクロール、ジェスチャー操作などを実現。建設現場では複数人が同時に図面に書き込みながら打合せが可能。Windows10/11のタッチ操作に最適化され、直感的な操作性を提供。タッチポイント数は機種により10点から40点まで対応。
-
VESA規格
ディスプレイの取付け穴の国際標準規格。100×100mm、200×200mm、400×400mmなど、画面サイズに応じた規格が存在。建設現場では移動式スタンドや壁掛け金具の選定時に重要。耐荷重や可動範囲も考慮し、安全な設置を実現。大型ディスプレイでは600×400mm、800×400mmなどの規格も使用される。
-
静電容量方式タッチパネル
スマートフォンと同じ原理で、指の静電気を検知するタッチ技術。高い透過率により画質劣化が少なく、軽いタッチで反応。マルチタッチ対応で、複雑なジェスチャー操作も可能。ただし手袋着用時は専用の導電性手袋が必要。建設現場では、精密な図面操作が求められる設計確認や、クリーンな環境での使用に適している。ガラス面の強度も高く、長期使用に耐える。
-
赤外線遮断方式タッチパネル
画面周囲に配置した赤外線LEDとセンサーで、遮断位置を検出する方式。手袋着用時でも確実に反応し、建設現場での実用性が高い。ペン、指、手袋など接触物を選ばない。大型化が容易で、100インチ超の電子黒板でも採用。ただし周囲のベゼル(枠)が必要で、完全なフラットデザインは困難。埃や水滴による誤動作を防ぐ補正機能も重要。
-
電磁誘導方式(EMR)
専用ペンから発する電磁波を検知する高精度入力方式。筆圧検知により、線の太さや濃淡を表現可能。手の接触を無視するパームリジェクション機能により、紙に書く感覚で使用できる。建設図面への詳細な書き込み、寸法記入に最適。ワコム社の技術が代表的で、プロ向けCADソフトとの相性も良好。ペンは電池不要で、紛失防止用のテザーも装着可能。
-
アンチグレア処理
ディスプレイ表面の反射を抑える特殊加工。建設現場の強い照明下でも、映り込みを軽減し視認性を確保。微細な凹凸により光を拡散させる方式と、特殊コーティングによる方式がある。タッチパネルでは、指紋や皮脂汚れも目立ちにくくなる利点も。ただし、若干の解像感低下があるため、高精細表示が必要な場合はグレア(光沢)タイプとの使い分けが重要。
-
ベゼルレス設計
画面周囲の枠(ベゼル)を極限まで細くした設計。複数台を並べて大画面を構成する際、継ぎ目が目立たずシームレスな表示を実現。建設現場では、巨大な図面や工程表を分割表示する際に有効。ただし、赤外線タッチ方式では技術的制約があり、静電容量方式やカメラ方式との組み合わせが必要。落下時の画面保護も考慮した設計が求められる。